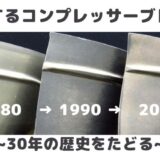飛行機の鼻先には高性能な気象レーダーが装備されている。
・飛行機に搭載されている気象レーダーは、飛行ルート上の前方の悪天候地域や積乱雲など危険な雲を探知できるシステム。安全で快適な飛行に必須の最重要装備。
その探知距離は 最大 200~300nm(370㎞~555㎞)
また、エレクトロニクスの進歩によって、雲だけでなく雲中のタービュランス域や危険なウインドシアまで予測できる。

画面に映し出される雲の状態
 Transaero_777_landing_at_Sharm-el-Sheikh_Pereslavtsev.jpg: Alex Pereslavtsevderivative work: Altair78 (GFDL 1.2, GFDL 1.2 または GFDL 1.2), ウィキメディア・コモンズ経由で
Transaero_777_landing_at_Sharm-el-Sheikh_Pereslavtsev.jpg: Alex Pereslavtsevderivative work: Altair78 (GFDL 1.2, GFDL 1.2 または GFDL 1.2), ウィキメディア・コモンズ経由で
現代の旅客機のほとんどが、飛行に必要な情報を全て集約して画面に表示している。その一つのND(ナビゲーション・ディスプレイ)には、カーナビのように飛行ルート・自機の位置・気象レーダーの情報などがまとめて表示されています。
前方にある雲がどれくらい危険なのか、その状態を 緑(軽い降雨)・黄色(通常の降雨)・赤(豪雨)と3段階に分けることで、一目で判断できるようになっている。
フラットプレート・アンテナ
 tataquax from Japan, CC BY-SA 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で
tataquax from Japan, CC BY-SA 2.0, ウィキメディア・コモンズ経由で
・B747-400やB767以降のデジタル化が進む時代に入ると、レーダーの発振装置も従来のマグネトロンから半導体素子に置き換わり、アンテナもパラボラ型から平板のフラットプレート型に変更された。
半導体素子を使用した送信機は周波数変動が少ない安定した送信ができ、受信ノイズも少ないことから対象物を鮮明に捉えることが可能となった。
コンピューターと融合したことで悪天候域の雲の状態をカラーで表示でき、より指向性の鋭いフラットプレート・アンテナによって雲の状態を細かく検出できるなど気象レーダーが大幅に進化した。
タービュランス(乱気流)の探知・ウインドシアの予測
タービュランス(乱気流)

水滴の集まりである雲。
その中で乱気流(タービュランス)が発生していると、雲中の水滴は激しく動き回っている。
大雑把な表現になりますが、静止している水滴に電波が当り戻ってくるだけなら同じ周波数ですが、水滴が激しく動き回っているとドップラー効果によって周波数が変動します。
受信した周波数の幅の広がりを測定することでタービュランスエリアを探知できます。
例えば
・送信(9.4GHz)→受信(9.4GHz) 前方に雨雲
・送信(9.4GHz)→受信(9.3~9.5GHz)雨雲+乱気流エリアがある
・送信(9.4GHz)→受信(9.2~9.6GHz)雨雲+激しい乱気流
(あくまで例えです。実際はこのような数値ではありません。)
ウインドシア
 作者のページを見る, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で
作者のページを見る, Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で
・急激な下降気流を引き起こすダウンバーストやウインドシアは、低高度を低速度で飛行している離着陸時に遭遇すると厄介な気象現象。過去には多くの航空事故が発生しています。
このウインドシアの予測も、タービュランスの検出機能を応用した技術が使われています。
先述のタービュランスは、反射する周波数がどの程度変動しているのかその幅で強弱を解析。それをさらに発展させ、どの場所で周波数が変動したのかを解析することでウインドシアを予測しています。
例えば、
・送信(9.4GHz)→A(9.5GHz)→B(9.4GHz)→ C(9.3GHz)
(あくまで例えです。実際はこのような大雑把ではありません。)
前方に送信した電波が、A B Cのような周波数で反射して戻ってきた場合。B地点に下降気流の中心があり、まもなく機体がダウンバーストに突入することが予測できる。
さいごに

高度1万メートルを超える巡航飛行中、気象レーダーは最大 370~550㎞先の悪天候を探知できる。これは、東京から直線距離で名古屋・大阪あたりの距離に匹敵する。
これほど遠くの気象状況を調べる理由は、その飛行速度にある。
地上で生活していると370㎞先は遥か彼方というイメージだが、飛行機ならわずか30分程度。もし飛行に大きな影響を与える悪天候なら、回避や迂回を考えなければあっという間に危険な雲に突入する。
それほど飛行機は高速で移動している。
天気の上を飛ぶと言われる現代の旅客機ですが、赤道付近で発生する積乱雲は強大なエネルギーによって成層圏付近まで到達する。万が一、気付かずに突入すると大変なことになる。
昼間なら目視でも視認できるが、夜間飛行だと気象レーダーがパイロットの目としてサポートする最重要なシステムとなる。

【参考にした本】